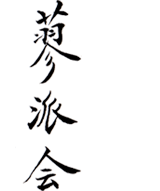小唄とは
小唄は花柳界の御座敷という特殊な世界で誕生し、江戸時代末期から明治、大正、昭和と発展し、現在まで伝えられている、粋と色気が最も大切なテーマの三味線音楽です。
花柳界と音楽文化
三味線音楽というと歌舞伎なども同じく、何か格調高く、難しいものと思われがちですが、実際は当時の若者の最先端の音楽芸術で、その演奏者はスター的、アイドル的な存在でした。
ヒット曲だけではなく、その演奏者のファッション、髪型生き方までが日本中を席巻したのです。あまりに過激で社会現象となったようなものは幕府から禁止令が出ることも多々あり、ビートルズやローリングストーンズなどと同じように若者文化を牽引していました。
当時の花柳界は総合芸術教育システム(芸能以外にも高度な文化教育を施した)であり、多くの芸術家を育て、それを楽しむ文化人のサロンやファンクラブの役割も果たしていました。
小唄の特色
小唄は撥を使わずに爪弾きの三味線のやさしい音色に乗せて、男女の微妙な恋愛心情や季節の移ろい、芝居の名場面、人生の哀歓、時事的な風刺などが洒落た詞章に凝縮されて演奏されます。唱法はあまり声を張らずにソフトに唄います。
詩歌の世界の俳句や川柳に似ています。季節にこだわり、掛け言葉に様々な意味を込め、節には色々な邦楽の調べを取り入れて作られています。一曲の演奏時間は2分前後のものが多く、長くても4分前後です。
小唄は能楽、古曲、歌舞伎音楽、民謡、祭囃子、相撲甚句など様々な伝統音楽のエッセンスで出来ているので、伝統音楽への入り口として実際にお稽古をするのに最適です。本来は、様々な伝統音楽を究めてから楽しむものが小唄でしたが、その逆もまた真なりで、小唄から入って、色々な邦楽の世界に出会うことが出来るのも魅力です。
小唄NOW
終戦後、日本の経済力が高まるにつれ、政財界の料亭接待の習慣化に伴い、小唄ブームが起こり、紳士の嗜みの一つにもなり、サラリーマンやOL、主婦層にも受け入れられ、ヒット曲が数多く生まれ、レコードも沢山売れた時期もありました。ところが、バブル絶頂期に起きたカラオケブームに押され、バブル崩壊後の花柳界の衰退とともに、小唄ブームもその影響を受けるところとなりました。
現在、小唄人口は減少しましたが、真にその音楽を楽しむ愛好家によって、古典小唄(江戸小唄等)も唄い継がれ、劇場用の新曲も数多く作られ、進化し続けております。
個人稽古やカルチャー教室では若い世代の入門も増えております。
全くの初心者の方、一度聴いてみたいと思っている方、是非一度、生の小唄演奏を聴きにホール、劇場、お稽古所見学などにお出かけ下さい。このHPにも随時演奏会やお稽古所の情報を掲載致します。

小唄四季折々
小唄の解説は、曲名をクリックして下さい。別ページで開きます。
解説:蓼 蝶弥
初出見よとて |
三下り 替手本調子
初出見よとて 出をかけて まず頭取の伊達姿 |
浮気うぐいす |
本調子
浮気鶯ひいふうみ まだ住み慣れぬ庭づたひ |
門松に |
二上り
門松に一つ止まった追羽根の それから明ける年の朝 |
めぐる日の |
本調子
めぐる日の 春に近いとて老木の梅も若やぎて候 しほらしや しほらしや |
春風がそよそよ |
本調子
春風がそよそよと 福は内へとこの宿へ 鬼は外へと 梅が香そゆる |
それですもうと |
本調子
それですもうと思うてかいな つのめ立つのも恋の欲 |
夜桜や |
三下り 替え手本調子
夜桜や浮れ烏がまひまひと 花の木陰に誰やらが居るわいな |
八重一重 |
三下り
八重一重 山も朧に薄化粧 娘ざかりは よい桜花 |
春霞(浮世) |
三下り
春がすみ 浮世は瓢箪さくらかな |
春雨に(相合傘) |
本調子
春雨に相合傘の柄漏りして つい濡れそめし袖と袖 |
茶のとが |
本調子
茶のとがか 寝られぬままの爪弾に 浮川竹の水調子 |
| 新派花柳章太郎 没後50年に際し、花柳章太郎ゆかりの小唄二題 | |
あぢさゐ |
二上り
紫陽花の かの浅葱色 かの人の 紺の明石の雨絣 |
本牧更紗(首飾り) |
六下り
をやまとは不思議なものよ花あやめ ダンスホールのくずれより |
上手より |
本調子
上手より はやしの船や 影芝居 あやなす手先 うつし絵や |
筆のかさ |
本調子 替手三下り
筆の傘 焚いてまつ夜のかやり火に さっとふきしむ |
川風 |
本調子
川風につい誘われて涼み船 文句もいつか口説して |
夏の雨 |
本調子
夏の雨 しのぎし軒の白壁へ 憎や噂を まざまざと |
散るはうき |
本調子
散るはうき 散らぬは沈む もみぢ葉の |
月は田毎 |
六下り
月は田毎にうつれども 誠の影は只一つ |
虫の音 |
本調子
虫の音を とめて嬉しき 庭づたひ 開くるしをり戸 桐一葉 |
露は尾花 |
本調子
つゆは尾花と寝たといふ をばなは露とねぬといふ |
雪のあした |
本調子
雪のあしたの朝ぼらけ 浪花の浦の真帆片帆 |
木枯し |
三下り
木枯しのふく夜は ものを思ふかな 涙の露の菊がさね |
初雪に |
本調子
初雪にふりこめられて 向島 二人が中に置炬燵 |